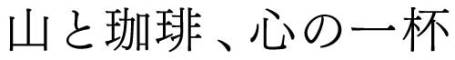富士山弾丸登山が話題になっています。
富士山での弾丸登山とは、夜に富士山5合目を出発して御来光を見るため睡眠をとらずに一気に山頂を目指す0泊2日の登山行程を意味します。
2011年に富士山環境保全協力金協議会から弾丸登山の自粛が呼びかけられ、自治体や山小屋・旅行会社や登山店などで「STOP弾丸登山」の告知がされています。
今日の富士山の天気は穏やかですが、軽装での夜間における弾丸登山は大変危険です。
高山病や低体温症のリスクが高くなるだけでなく、登山渋滞や落石などが発生する原因になります。
夜間に五合目から登り始めることは控えていただくようお願いいたします。 pic.twitter.com/j4pNp4fUSI
— 山梨県富士山五合目総合管理センター (@FujisanInfoC) July 31, 2023
でも、なんで「弾丸」なんでしょうか。

「弾丸」と名付けられた由来や理由、代わりの言葉などを考えてみました。
JTBが定義している「弾丸旅行」が由来?
弾丸の主な意味は「銃砲で打ち出すたま」ですが、「弾丸列車」(弾丸のように高速で走る列車)という使われ方もあります。

※ なお、「Bullet Train」と英語にすると、「新幹線」を意味する単語になります。
そして、JTBが2001年に商標登録したのが「弾丸ツアー」。弾丸ツアーとは、日帰りや車中泊・機中泊を利用して宿泊せずに観光する短期旅行という意味です。

「弾丸登山」というネーミングの課題と問題点
この弾丸登山には、2つの課題と問題点があると私は思っています。
1つは、文字を見てすぐに内容が理解できないという点。
まず「弾丸=早く登る」というのが万人に理解されにくい。また、早く登るとどんな問題があるのかも文字だけではわかりにくい。「ストップ弾丸登山」といわれても、じゃあどうしたらいいのかがわからない。
できれば何か標語(キャッチコピー)を添えてアピールした方が良いように思います。

もう1つは、弾丸登山(Bullet-climbing)という言葉がカッコいいという点です。
弾丸のように早く登り、目的を達成して帰還する。夜通し歩くという困難に立ち向かう。体力の限界に挑戦する。
この「困難への挑戦」は達成した場合「偉業」となってしまいます。
また、英訳の「Bullet-climbing」というワードも、命知らずで冒険好きな外国人を逆に刺激するような気がします。

弾丸登山の代わりの言葉を考えてみた
弾丸に代わる、良い言葉はあるのでしょうか。思いつくワードを列挙して考えてみました。
1.「強行登山(きょうこう-とざん)」
視覚的わかりやすさ:☆☆☆☆
言い易さ:☆☆☆☆
聞き取りやすさ:☆☆
カッコ悪さ:☆

2.「限界登山(げんかい-とざん)」
視覚的わかりやすさ:☆☆
言い易さ:☆☆☆☆☆
聞き取りやすさ:☆☆☆
カッコ悪さ:☆

3.「富士山大返し(ふじさんおおがえし)」
視覚的わかりやすさ:☆
言い易さ:☆
聞き取りやすさ:☆☆
カッコ悪さ:☆☆☆☆

4.「無鉄砲登山(むてっぽう-とざん)」
視覚的わかりやすさ:☆☆☆☆
言い易さ:☆☆☆☆☆
聞き取りやすさ:☆☆☆☆☆
カッコ悪さ:☆☆☆☆

5.「突貫登山(とっかん-とざん)」
視覚的わかりやすさ:☆☆☆☆☆
言い易さ:☆☆☆☆☆
聞き取りやすさ:☆☆☆☆☆
カッコ悪さ:☆☆☆☆

こんな感じで、私は「突貫登山」を推したいです。
「弾丸登山」に比べてカッコ悪く、強引さや無謀・無計画なニュアンスが入っているわかりやすい言葉なんじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
キャッチフレーズも「ストップ!突貫登山 ~富士山は泊まって登ろう~」 あたりで大々的に告知をすれば、「富士山は泊まって登るものなんだ」という認識が広がりそうかなと思います。

【まとめ】弾丸登山自体は別に悪くない
非難されている「弾丸登山」ですが、弾丸登山自体は決して悪いことではありません。
十分な体力・経験・装備が整った人なら可能で、山を駆けるトレイルランナーなどは富士山5合目~山頂を3時間くらいで往復してしまいます。
悪いのは、体力が無いのに下調べや十分な準備もせずに登って低体温症や高山病を引き起こす観光客です。
ただ、宿泊推奨とはいえコロナ対策で山小屋の収容人数が昔より減り、宿泊予約自体が取れにくくなっています。
「富士山には登りたいけど宿が取れない」という人が突貫登山を考えてしまうのは仕方ないことかもしれません。
パッと思いつく解決法は、
「宿泊予約した人だけ登れる入場制限をする」
「農業用モノレールなどで5合目から山頂までつなぐ」
「テント泊ができる大収容エリアを新設する」
あたりですが、どれも決定・実施に時間がかかります。
そして、そもそもの遭難者数の割合も全体から見ると少ないです。
昨年度の夏富士での死亡者数は6名。遭難事故は約60件。登山者数は約16万人なので遭難率は0.0003%(死亡率0.00003%)です。
60名(6名)を相手に、大掛かりな予算が必要なシステムやインフラを整えるのは難しいと思われます。
当面の間は警告看板や標語の普及で地道にやっていくしかないかなと思います。

【この記事も併せてどうぞ】