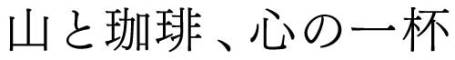霧が発生している高山で日の出や日没時に太陽を背にすると、霧に自身の影と虹の輪が浮かぶ「ブロッケン現象」が発生します。

このブロッケン現象の「ブロッケン」とはどういう意味なんでしょうか。
名付けの由来となった場所についてや、人工的に作る方法などについて調べてみました。
目次
言葉の意味・由来となったブロッケン山について
まずは「ブロッケン」という言葉について。
ブロッケン(brocken)はドイツ語で「(大きく形のない)かたまり」を指すそうです。
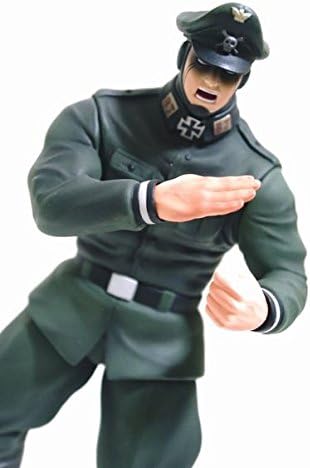
【amazon】CCPマスキュラー コレクション Vol.056 ブロッケンJr.


そして、ドイツの中央部・ハルツ山脈にはブロッケン山(標高1141m)があり、この山が「ブロッケン現象」の名前の元となっています。


引用:【Wikipedia】Brocken (photo:Gemeinfrei)
ブロッケン山(別名:Blocksberg/ブロックスベルク)は気候が標高2000m級で年間300日は霧に覆われるため、ブロッケン現象が発生しやすい環境となっています。
1780年にドイツの自然科学者ヨハン・エサイアス・シルベルスラグが論文に記して正式に名付けられました。

引用:【Wikipedia】Brocken (illustration: Johann Heinrich Ramberg,)


引用:【amazon】ファウスト 1 (岩波文庫) 文庫/ゲーテ (著)
ブロッケン現象の日本語表現といつから呼ばれたのかについて
このブロッケン現象(Brocken spectre:ブロッケンスペクター/ブロッケンの亡霊・妖怪)は、日本では「御来迎(ごらいごう)」または「(山や仏の)後光(ごこう)」などと呼ばれ、阿弥陀如来との邂逅だとされていました。
ブロッケン現象の論文が発表された1780年からさかのぼる事およそ100年、松尾芭蕉の弟子で旅の同行人・河合曾良(かわいそら)による1689年の「曾良旅日記」に「出羽三山の修験者が来迎(らいごう)と名付けた」という記録もあるそうです。
また、富士山の山頂でも御来迎は見られ、富士講の始祖・長谷川角行が富士山で修行を始めたのは1563年。富士講が流行した1600年頃にはすでに「御来迎」という言葉は生まれていたのかもしれません。

人工的なブロッケン現象の作り方・再現方法について

引用:【wikipedia】ブロッケンの亡霊 撮影:ボブ・ブレイロック
この神秘的なブロッケン現象、霧が発生していれば太陽が無くても作り出すことができます。
霧がかかっている方向に向かって立ち、背後から車のヘッドライトをハイビームで当てると自作ブロッケン現象の完成です。

光量の多いフラッシュライト・懐中電灯
GENTOS(ジェントス)
アルティレックス UT-226R
10500ルーメン

GENTOS(ジェントス)
アルティレックス UT-618R
13000ルーメン



ThruNite(スルーナイト)
TN50
16340ルーメン