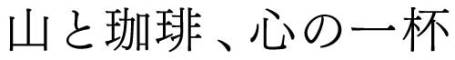引用:足利市「『足利市の美しい山林を火災から守る条例』が制定されました!!」
栃木県の足利市にて、令和4年(2022年)4月1日から「足利市の美しい山林を火災から守る条例」が施行されました。
足利市内の山林の屋外では、たばこ(電子タバコ含む)・たき火・花火・携帯コンロやストーブ・バーナーなどの使用が禁止となりました。

条例が出来た理由と、条例の全文や罰金について、予想される今後の規制や何か有効な対策はないのかを考えてみました。
目次
条例実施の理由と背景

引用:足利市「災害記録誌「足利市西宮林野火災の記録~火災の概況と本市等の対応~」
条例実施の要因となったのが、2021年2月に発生した大規模山林火災。焼失面積167ヘクタール、消火活動の人数は約2000人、305世帯に避難勧告が発令され、鎮火まで23日間を有しています。

失火場所とされているのは、柴山の山頂。標高251mの両崖山(読み方:りょうがいさん)から天狗山に向かう途中の脇道にある山で、山頂の木製テーブル脇にたばこの吸い殻が数本あったそうです。
「足利市の美しい山林を火災から守る条例」の全文について
「足利市の美しい山林を火災から守る条例」は、こちらのページから全文を確認することができます。
「足利市の美しい山林を火災から守る条例」全文 [PDFファイル/147KB]
条例違反の罰則・罰金について
条例内容を確認すると、実際に山で火を使っても即罰金・罰則となる訳ではないようです。
もし火が燃え広がって、「他人の森林放火」となったなら1年以上10年以下の懲役、または森林法にて2年以上の懲役(放火の場合)・50万円以下の罰金(失火の場合)、という参考例が条例制定告知ページに併記されていました。

予想される今後のバーナー規制
今回の「足利市の美しい山林を火災から守る条例」は罰則なしなので、取り締まりなどの準備や手間・経費をかけずに迅速な施行が可能です。
参考例として、「歩きスマホを規制する条例」は罰則なしで、2020年7月に神奈川県大和市が全国初で施行したあと、12日後に東京都足立区が施行して、その後複数の自治体が同じような条例を採用しています。

環境省の見解では「自然公園法上はコンロは規制の対象外」「利用調整地区でも(小型火器の使用は)認められる」(※1)としているため、これまで自治体は「火の取り扱いには注意を」というレベルでしか規制できませんでした。足利市の条例を契機に、過去にボヤなどがあった自治体では同様の条例の施行を検討しているかもしれません。
バーナーを使っての山ごはんや山コーヒーが一部の山好きの間でブームになっているとはいえ、ユーザー数は一般観光客数に比べれば少ないと思われます。バーナー利用を禁じたところで管理側には大きな経済的損失はないでしょう。
むしろ、火災発生リスクを大きく減らせるうえ、地元の弁当や食料品、食堂を利用してもらえるなどの売り上げを生み出すことができます。
※参考1「第五回吉野熊野国立公園西大台地区利用適正化計画検討協議会議事録」
http://kinki.env.go.jp/nature/odaigahara/saisei/pdf/tekiseikakyougikai/h18_w5_02.pdf
どうやったらバーナー・ストーブは受け入れられるのか
足利市の条例が生まれたきっかけは「タバコのポイ捨て」だったのに、なぜ携帯コンロも規制されることになったのか。
私が想像するに、誰でも簡単に購入できて安全講習なしに使用できるという点が大きく影響しているのではないでしょうか。
もし、「登山用バーナーを購入・使用するには国家資格の危険物乙四資格が必要」という仕組みがあったりしたなら、火災事故の発生件数は下がり、足利市の条例にも「ついでに併記」されることはなかったように思います。
「じゃあ一般的なカセットコンロを使うのにも資格が要るのか? カセットコンロと登山用バーナーは何が違うのか?」と聞かれると返答に困るのですが、要するに山の管理側に安心していただくためのアクションを起こすべきだと思うんです。例えば「登山用バーナーやストーブの販売業者が安全講習会を実施する」などがあれば印象も良くなります。

屋外でドローンを飛ばすときのような許可申請式になっても良いと思います。なにもしなければ、近い将来「登山用こんろはテント場・指定のエリア以外では使用禁止」という風になっていくのではと危惧しています。ひとまずはまた大きな山林火災事故が起こらないことを願うばかりです。
追記:火を使わないバッテリー式湯沸かし器


Cauldryn
Coffee Smart Mug
なお、私が火気厳禁の奈良の吉野山で使ったのがモバイルバッテリーの力で100℃まで沸騰させることができる携帯型の過熱トラベルマグ。これなら火気厳禁の山域でも水からお湯を作れます。欠点は、サイズが大きいことと重いこと。重さは1072gで、登山に持っていくにはちょっと気になる重さ。また、満充電状態でも2回しか沸騰できません。あと、私は海外から入手したのですが最初に取り寄せたものは水漏れがしたので交換しました。海外品なので故障時の交換が面倒です。廃棄についても、自治体によっては海外製バッテリーの処分がややこしいかもしれません。
もっと買いやすくなるよう、今後日本で販売代理店ができれば良いなと思っています。