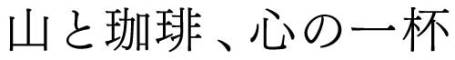恩田陸さんの短編小説「珈琲怪談」、作品内に出てくる喫茶店特定の第5回です。
第1回はこちらから。
珈琲怪談Ⅴ(第5章)は大阪のキタからミナミが舞台。小説の初出は小説幻冬2024年3月号と4月号です。
大阪の街にも、大阪万博の名残を感じる名店・大大阪時代の名店があります。作中人物が訪れたであろう喫茶店、特定していきたいと思います。
目次
【1軒目】マヅラ喫茶店
梅田の大きなビルの地下街で「不思議な空間、昔のSF映画のセットみたいだ」という内装。大阪駅前第1ビルB1の「マヅラ喫茶店」がモデルと思われます。
開業は1947年。当初はアメリカから輸入した電気蓄音機が売りの名曲喫茶でした。店名は創業者が学生時代に旅した思い出の場所、インドネシアのマドゥラ島から名付けられています。

マドゥラ島は伝統文化と自然が魅力。「カラパンサピ(牛レース)」、手つかずのビーチ、塩田風景、風味豊かなサテ・マドゥラ(焼き鳥)など、素朴で力強いインドネシアのローカル体験が楽しめます。
1970年代の大阪駅前再開発により、マヅラは駅前第1ビルの中に移転。1970年に大阪万博が開催されたことから未来や宇宙をテーマにした内装を採用されたそうです。この内装には「日常を忘れてリフレッシュできる空間を提供したい」という創業者の思いが込められています。2014年には魅力ある建物を市が発信する「生きた建築ミュージアム」に選ばれました。
●値段は昭和。
コーヒーが税込300円です。ミックスジュースも350円でドリンクはほとんど500円以下。喫茶店スタイルでこの価格は安いです。

尾上が注文した「絵に書いたようなプリンアラモード」はこちらですね。
気になった部分を深掘りしてみた①
●スターバックスコーヒーは荒川区に一軒もない
荒川区は学生が少ないのでスタバが来ないのだと言われていましたが、2023年7月14日にLaLaテラス南千住にスターバックスコーヒーの店舗が入りました。
●黒田の家の近所はスタバが信号渡るたびにある
スタバが密集している地域は全国にいくつかありますが、黒田が住んでいるのは町田駅あたりかなと思っています。町田のスタバは6店舗あり、町田駅からは新宿・渋谷・横浜へ乗換なしで出られるので都内各所の捜査にも出やすいです。
●尾上「おめざだよ、おめざ」
おめざとは、子供が朝起きたときに与えるお菓子のこと。石川県には朝食前後に甘いものをちょっと口にするという風習が根付いています。
●「妹(いも)の力」
「妹の力」は、古代社会において女性(特に妹)が霊的・社会的な力を持ち、兄の運命や地位に大きく影響を与える存在であったという民俗的観察を示す概念。
●「大阪人て、日本一歩くのが速い」?
統計データによると早歩きの割合が最も高いのは神奈川県で、次いで東京都、大阪府という結果が出ているそうです。ただ、「大阪人は歩き出しが早い」という特徴があり、これが速いというイメージにつながっている可能性があるようです。
●当時ってゴミ袋が黒かった
東京都のごみ袋が黒色から透明(半透明)に変わったのは2013年10月。ごみの中身確認をしやすくして分別ミスの削減や不法投棄を減らすために実施されました。
【2軒目】Mole and Hosoi Coffees(モール&ホソイコーヒーズ)
幹線道路から一本入ったレトロな古いビルの地下のカフェで、ビルが大大阪時代の遺産といえば、モデルになっているのは中央区の「モール&ホソイコーヒーズ」だと思います。
淀屋橋の有形文化財「芝川ビル」地下の元金庫室に2008年に開店。店名は地下で静かに営む様子を「モグラ(Mole)」に例えたもの。9席のカウンターのみで、一人客が落ち着ける空間と丁寧に淹れたコーヒーが魅力。

昔ここによく通っていました。アルコール入りのアマレットコーヒーがお気に入りでした。9席しかないので、グループで入れたら奇跡という感じです。
気になった部分を深掘りしてみた②
●尾上の「まだらの紐じゃなく?」という言葉
「まだらの紐」(まだらのひも、The Adventure of the Speckled Band)はアーサー・コナン・ドイルによる短編小説。ホームズ短編中の最高評価を得ている傑作です。
●ここは国の有形文化財に登録されているはず
芝川ビルディングの竣工は1927年。古代マヤ・インカの細部装飾を採入れたアールデコ建築で、国の登録有形文化財には2006年10月18日に登録されました。
●大阪といえば必ずTVの画面に映るあの超有名な一角
モールホソイコーヒーから3軒目へ向かって歩いている途中の「大阪の超有名な一角」といえば、道頓堀・戎橋(えびすばし)のグリコの看板のことだと思います。


このグリコの看板は1935年に初登場し、当初はネオンでした。現在は6代目でLEDになっています。
●山陰の「こわい店」
山陰の海岸線でこのわた・いか塩辛の看板が出ている店を探しましたが見つけられませんでした。「このわた」はナマコの内臓の塩辛で日本三大珍味のひとつ。山陰では鳥取県の境港市、島根県の松江市や浜田市、兵庫県新温泉町の浜坂などが名産地です。
【3軒目】丸福珈琲店 千日前本店
南北に延びるアーケードの通りからちょっと路地に入ったところのレンガ造りを模したどっしりした構え。「丸福珈琲店 千日前本店」がモデルと思われます。
1934年創業の老舗喫茶店で、戦後に大阪市西区江戸堀から千日前へ本店を移転。創業者の伊吹貞雄氏が独自開発した深煎り珈琲は、濃厚でコク深い味わいが特徴。アンティーク調の重厚な雰囲気は「ミナミの応接間」とも称され、多くの文化人や芸人に愛されてきました。
引用:丸福珈琲店 千日前本店

確かにインテリアは重厚感があり、窓のステンドグラスも鮮やかです。
気になった部分を深掘りしてみた③
●三遊亭円朝について
三遊派の総帥で宗家。「近代落語の祖」として有名。代表作は「怪談牡丹燈籠(ぼたんどうろう)」など。怪談噺の参考とした幽霊画のコレクターとしても知られ、遺されたコレクションは「圓朝まつり」や展覧会などで公開されています。
●水島の実家の庭に咲いていた山茶花の花

山茶花(さざんか)は晩秋から冬にかけて咲く花で、冬場に庭に彩りを与える貴重な存在。密に枝葉が茂るので生け垣や目隠しになり、寒さや病害虫に強く、剪定にも耐えるので管理がしやすい植物として重宝されています。
山茶花は寒さにある程度強いのですが、厳寒地では育てるのは難しいとされています。水島の実家は秋田なので手入れを頑張っていたのだと思われます。

山茶花の花びらは比較的繊細で、特に開ききった状態のものは風雨にとても弱いので「ひと晩で全部散る」ということは有りえるそうです。
●黒門市場の海産物が軒を連ねるアーケード
黒門市場は1822年頃に魚商人が市を開いたのが始まりで、「黒門」の名は1912年までこの地域にあったお寺・圓明寺の門が黒塗りだったことからとされています。昔は地元の料理人や一般客が新鮮な食材を求めて訪れる市場としての役割が中心でしたが、2010年頃から訪日外国人観光客が増加し、海鮮丼や串焼きなどのメニューが提供されるようになりました。

コロナ前のインバウンドブームの時は英語ばかりで大賑わいでした。
【4軒目】伊吹珈琲店
黒門市場のアーケード街の外れにある、昔ながらの喫茶店。常連が市場関係者、昭和の家の洋間。確定できる情報が少ないです。
黒門市場の外れにある喫茶店は、「コトブキ」「伊吹珈琲店」「ボニー」「コンドル」「六覺燈カフェ」「Cafe Sun Bird」「明日香」「喫茶ひろ」「珈琲スモール」「おいで」「果林」など。
この中で、黒田の「コンセプトは似てる」という発言部分に注目するなら「伊吹珈琲店」あたりがモデルの店かなと思います。
ここは元々「丸福珈琲店 黒門市場店」が営業していましたが、1991年に「伊吹珈琲店」として独立。独自のブレンドやサービスを提供するようになりました。店名の由来は丸福珈琲店の創業者・伊吹氏の名前から。


アンティークが並べられています。コーヒーも丸福のような濃い目なので「ガツンとコクがある」という記述の通りです。
気になった部分を深掘りしてみた④
●黒門市場の近所にある大阪一古いという神社
黒門市場の近所にあるのは生國魂神社(いくたまじんじゃ)です。2700年の歴史がある大阪で最も古い神社で、「いくたまさん」の愛称で親しまれています。日本の初代天皇・神武天皇が日本列島そのものの神である生島大神・足島大神を祀り、国土の平安を願ったのが発祥とされています。
●神社の前を通り過ぎたら崖縁占のブースがあった
生國魂神社の境内にある「崖縁占(がけっぷちうらない)」は、土日祝の10時~16時に行われ、鑑定料は30分3000円(相性占いは5000円)だそうです。人生の岐路に立たされたような「崖っぷち」の状況にある人々が主な対象で、ユニークな名前と的中率の高さから多くの人々に親しまれています。
引き続き最終章も特定していきたいと思います
「珈琲怪談Ⅴ」の大阪編には私が行ったことある店が出てきて嬉しかったです。
あの空間で4人が怪談している姿を想像すると、妙な親近感がわいて怪談のリアルさも一層引き立ってきます。
聖地巡礼、機会が合う方はぜひオススメしたいです。

なお、今回のおおよその歩行距離は5.2km。歩行時間は1時間15分。毎回思うんですが、「怪談ウォーキング」って良い運動ですね。
次回は最終章です。引き続き、楽しんで特定作業をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
珈琲怪談
恩田 陸 (著)

続きの第6章(最終章)はこちらです。