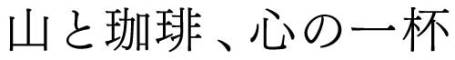登山地図アプリを提供しているYAMAP(ヤマップ)。サービスの一部変更がアナウンスされ、SNSで話題になっています。
これまで無料ユーザーは登山地図を制限なくダウンロードできていましたが、2021年3月1日(月)からは「無料ユーザーは地図ダウンロードが1ヵ月に2枚まで」となります。

ユーザーからの想定以上の反響を受けてか、YAMAP側がyoutubeで説明会を開くことになりました。
この会見なのですが全体の長さが1時間30分(説明パートは約45分)あり、しかも結論から入らないプレゼン形式でした。「話が長い…!結局理由はなんなんだ…!」と、途中でギブアップした人も多いと思います。
テキストでザっと見られるように、要点と私の所感を書いていきたいと思います。
なお、私の所感の結論を3行でまとめると
「利用者が増えてきて維持管理が大変でコロナの打撃もあったなら有料化は仕方ない」
「地図アプリ業界で足並み揃えてすべて有料月額制にしてもいいのでは」
「ベンチャー企業で約60人の社員を抱えて常に成長を強いられているのは大変だな…」
です。
YAMAPの会社についての説明パート
> 本日は地図仕様の変更だけでなくYAMAPのビジョンや何のために企業したのか、代表の想いや会社全体のことをお伝えしたい。

> みなさんからのご意見は真摯に受け止めるので遠慮なくご意見ご質問をお願いします。

> 話したいことは3つ。「会社について」「現状について」「変更について」を3つのスコープ(見る幅)にわけて話していきたい。望遠で広く(会社として)ものごとを捕らえる、中サイズで現状を見る、クローズアップの狭い視界が変更について。

> YAMAPはベンチャー企業なので、新しい価値や新しい市場を作る・挑戦する・圧倒的な成長で社会に良質なインパクトを出すことが必要。主要業務のアプリウェブサービスは一強多弱の厳しい世界、大多数のユーザーの規模がないと生き残れない。震災以降の貧富の差・これからの人口減など日本経済の未来が貧しくなっていく危機感があり、今のうちにやれることをやって5年後10年後に社会インフラに育てたい。そのためには極端な経営が必要。

> なぜ起業したのか。日本社会の最大の課題は「身体をつかっていない」。農業や漁業など自然相手に体を動かしているのは人口の3%。残りの1億1千万人は日常的に体を動かしておらず、生物としてのバランスが悪くなっているのでは。2011年の震災を経て、自分たちがどういう風土・環境に育まれ、今を生き、次の世代にバトンをつないでいくのか。そういう知る機会を作らないといけないのではと想いで起業した。1次産業は新規参入が難しいが、登山やアウトドアは人と自然をつなげるのに可能性がある。登山GPSで山の事故を減らし、山や自然を愛する人たちを束ねながら登山人口を増やしていくことで、社会的意義を深めることができるのでは。

YAMAPの現状説明パート①
> YAMAPの現状について。社員数64人で登山・アウトドアベンチャーでは日本で最大規模。スマホアプリダウンロード数は226万件でMAU(月間利用者数)52万人、パソコンでのMAUは123万人。MAUも活動日記数も右肩上がりで順調に成長をしている。2019年11月までは「サービスが先、利益は後」というスタイル。ベンチャーはユーザー規模・ユーザー満足度が必要なため、運営費・開発費は約15億円の資金調達でまかなっていた。圧倒的な成長を目指すため、私利私欲のためではなく社会にインパクトを出すためにこれだけのお金を出してもらってリスクを背負った。

> 八方よしとは言え経営はバランス。持続可能な形になるよう会社を成長させないといけない。今までは「ユーザー>株主」で資金を使っていたが今後は「ユーザー=株主」でバランスを取りたい。2019年11月に140万ダウンロードを突破して登山人口700万人の2割に届いた。圧倒的規模の目安が17%~20%なのでひとつの区切りとなった。ここから「サービスも利益も、同時に追求」する会社、規模と質を育てながら健全な収益化にも挑戦する段階に入った。

> 「力なき志は無力」。社会にインパクトを出すために「力をつけたい」=「稼ぎたい」。収益を元により革新的なサービスを作って世に届け、持続可能な会社にしてユーザーと一緒に良いサービスを作っていきたい。

財務状況説明パート
> 第7期(2019.7~2020.6)の決算公告を官報に掲載。数字的に誤解されやすいので説明したい。約4億円の損失は赤字経営に見えるがサービス優先なので当初の予定通り。ただ、2020年4月からのコロナの影響が想定外。収益化に進めずに山小屋支援などを行った。このままでは危ないので資金調達を行い、財務は改善した。YAMAPが今すぐ倒産するということはない。

> ずっと資金調達できるわけではなく、収益化はいつかはやらないといけない。これからの1~2年で黒字化して2~3年後の上場を目指す。

YAMAPの現状説明パート②
> 再びYAMAPの現状、サービス展開や収益化の考え方について。登山(アウトドア)はニッチ市場。衣食住のメルカリ・クックパッドなどは市場が大きいので1つのサービスで収益化ができるが、YAMAPはひとつの施策で収益化するのが厳しい。登山人口が700万~1000万人、キャンプ人口が1000万人で多く見積もっても2000万人。登山もキャンプも毎日行かず月に何度か。登山以外の山関連のサービスを提供して健全に収益を増やしていかないと成長できない。

> ユーザーにあらゆるサービスを提供したい。1つ目は「高機能のアプリ有料会員」で収益を上げたい。もう1つは「保険」。1日で入れる保険はYAMAP保険の前には無かったので簡単に加入できる保険でユーザーの役に立ちたい。

> 道具の分野(YAMAPストア)でもサービスを展開し、メディア(YAMAPマガジン、企業向けのタイアップ広告)でも収益を上げて、ゆくゆくは自然観光やガイドのマッチングなど展開していきたい。

> 有料会員について。全YAMAPユーザーに有料会員になってほしい訳ではなく、20%がプレミアム会員になってほしい。80%は無料会員のままでも運営上問題ない。プレミアム会員の推移はスタート時の2020年1月で約8000人、3月に2万人、2021年1月で4万1500人。着実に増えているが、コロナの影響で想定より遅い。持続可能な会社にするために現状の8%から15%、プレミアム会員数8万人にしたい。

仕様変更説明パート
> 仕様変更の目的は「持続可能な会社にして良質なサービスを末永く提供し続けるため。(ユーザー離れが起きないよう)登山初心者やライトユーザーにも使っていただく仕組みを残しながら変更する」。登山人口700万人の約1%を目指したい。プレミアム会員数を今の8%から15%へ、無料会員を92%から85%にしたい。

> 無料ユーザーへの制限内容は「保存できる地図枚数を5枚から2枚」「月にダウンロードできる地図枚数を無制限から月2枚まで」。社内で検討した数値。自治体と連携している地図やトレラン大会の地図は制限対象外。

> 1日あたりだと10円。GPSアプリが出る前は65000円のGPS機器を使っていた。山と高原地図の紙地図は1エリアで1100円。YAMAPの月額290円は価値としては変わらないと思うしコストパフォーマンスの良いサービスが提供できる。決して高い金額ではないと思っている。

> 今後について。登山計画の機能を実装して自治体と連携を深めている。みまもり機能で遭難者が助かった事例があったのでこれは無料で提供したい。遭難時の対応(警察などへの情報提供)は休日問わず行っている。営利企業なら有料だがここは引き続き無料にしたい。これらの維持のためにもプレミアム会員を増加させたい。プレミアム会員向けの特典(特別機能・ストア割引・イベント招待など)も充実させる。

最後に
> 経営者や会社の立場、ユーザーの立場で色んな考えがある。YAMAPのサービスはユーザーと一緒に作ってきたので、会社の考え方や現状を共有して、今回の制限などについてユーザーと議論をしたい。持続可能な会社になるように一緒に育てて、人と山をつなぐビジョンを実現させて社会により良いインパクトを出したいと思っている。

Q&A
> ユーザーから双方向でQ&Aの対応。

※ かなりの数の質問があったので、今回の有料化に関する質問のみピックアップしました。
Q.さらに安いプラン、地図の個別売りを用意してほしい。
A.課金はシステム的に処理が難しく複雑。プランを増やすと負担が増えて別の部分の質が落ちたり新しい機能が作れない可能性がある。検討はしているが今はシンプルな1つのプランで運用させて頂きたい。

Q.今後値上げの可能性はあるのか
A.今のところは無い。ただ、アプリとwebの料金に差があるのでいずれwebの価格をアプリに合わせる予定。

Q.広告をたくさん載せていいから無料で使いたい
A.広告表示は検討したが、デザインがコントロールできずユーザーの使い勝手も悪くなる。広告ではなく事業で収益を得たい。2019年11月までは広告を少し載せていた。ただ月間PVが1億2千万なので、広告だけで数千万の利益が出せない。今のユーザー数だとすべてのページに広告を入れて動画で強制視聴させないといけない。ユーザーの使い勝手を優先したい。

Q.有料会員でも地図ダウンロードが50枚までに制限されるのか?
A.地図が「保存」できる数を50枚に制限した。元々無制限だったが、調査の結果外部のライブラリの影響ですごく(動作が)遅くなったりアプリがクラッシュすることがわかった。現在の端末の性能的に50枚がアプリが快適に動く限界。

Q.無料ユーザーを追い出そうとしているのか?
A.基本的にはそうは思っていない。80%の人は無料で使える設定にしたい。山に月に何度も行っていて地図を何十個もダウンロードしている人はなるべくプレミアム会員に移行して頂きたい。

Q.2019年11月の有料会員施策でユーザー数が減っている?
A.ユーザーの数は順調に成長している。よく他社と比べられているので今回資料を用意した。
YAMAP100/ソトシル約65/ジオグラフィカ17.2/ヤマレコ9.6/山と高原地図4.6
※アプリ分析サービス「AppApe」記事2020年8月6日より
【月間利用ユーザー数(MAU)の推移】
YAMAP280000/ジオグラフィカ40000/ヤマレコ30000/山と高原地図7000
※アプリ分析サービス「AppApe」
あくまで一例なので自分たちがすごいとかいいたい訳ではない。圧倒的に規模が大きいので社員数も多いしサーバーも増やしてインフラ整備をしないといけない。

Q.情報を絞って有料化するのではなく新機能を有料化して有料会員を増やさないとユーザー数の低下はSNS機能の縮小に直結する
A.利用者数が減れば活動日記や情報量も減るが、現状は大幅に減っていないので影響は少ないのではないかという見通し。

Q.地図をダウンロードしなくても中身をチェックできるようになれば無料の人の不安が減るのでは?
A.3月1日から「プレビュー」という機能で変更を行う。

Q.プロダクトやサービスそのもので課金が達成できないのであればそのマネタイズは失敗ではないでしょうか?
A.おっしゃる通り。便利さや使いやすさなどのプロダクトで課金いただくのが本筋。製品で勝負できていないのでより良い製品を作っていきたい。

青山の所感
説明パート45分、なかなか話が長かったですがYAMAP側が伝えたいことは十分理解できました。そこそこ利用しているユーザーは有料化すれば良いと思いますし、むしろ、あとちょっと価格を下げて全ユーザー有料化(最初の30日間はお試し無料)に踏み込んだほうがわかりやすいのではとも思いました。

説明会動画は核心部分の話になかなか入らないので動画の低評価数がどんどん増えていきましたが、最終的には盛り返してダブルスコアで高評価がまくり上げました。YAMAP側の想いが無事に届いたと思われます。
私が説明を聞いていて気になったのは、YAMAPの理念である「身体を使っていない(もっと山に行ってほしい)」が、「地図が無料なのは月2枚まで」によって若干の矛盾が生じている点。有料会員の人だけがたくさん身体を使えるということになり、「人と自然をつなげる」が少し建前のように聞こえてしまいます。維持と進化のためには収益化は仕方のないことですが。
地図データの実質有料化でユーザー数が減少する可能性は高いのですが、おそらく出て行くのは一部の無料ヘビーユーザーなのでサーバーの負荷が軽くなると思います。もう国内の主要な山の山行データは十分集まっているとしたら、月2回以下ダウンロードのライトユーザーと有料化を受け入れてくれる優良ユーザーを手厚くサポートすれば運営が効率的になるのだろうなと思いました。

はたして、来月3月1日の有料化でどれだけの数が動くのでしょうか。地図は登山者の命を守る重要な役目があり、そこを制限したことについては心証がよくありません。登山地図アプリのヤマレコは、YAMAPの説明会動画で「ヤマレコは登山者の1割も使ったことがない」と言われたことに対して代表の的場氏が「売られた喧嘩は買わなきゃなー」とコメント。ヤマレコのツイッターで「月あたりの地図ダウンロード上限なし」など、新規ユーザーへのPRを積極的に行っています。
競争が働けば業界全体のサービスは良くなっていくので、今後の展開が楽しみです。個人的にはYAMAPが上場して世界にサービスを展開できるような企業になってもらえたらなと思います。
■YAMAP(ヤマップ)
https://yamap.com/
■ヤマレコ公式ツイッター
https://twitter.com/yamareco